磯釣りを始める前に知っておきたい基本的なマナーと安全対策を紹介!磯釣りは足場が悪くスリルがある分、魚が釣れたときの達成感が大きいことが魅力です。
一方で、危険な場所も多く、マナーや安全対策を怠ると大きな事故につながることもあります。特に初心者の場合、「どこで釣っていいの?」「何を準備すれば安全?」といった不安を抱えがちです。
そこでこの記事では、磯釣りデビュー前に押さえておきたい基本ルールと安全のポイントをわかりやすく解説します。これから磯釣りを始める人は、ぜひチェックしておきましょう。

この記事を書いた人
F!ND編集部_コウイカ
現役マリーナスタッフであり、10年以上のマリーナ勤務歴がある。自身も釣りやが好きで、最近はジギングやエギングにハマっている。
磯(いそ)とは?

「磯(いそ)」とは、海岸線に沿って岩や岩礁が露出している場所のことを指します。砂浜とは違い岩が多く起伏があるため、波の力が強く潮の流れも複雑です。
磯場は隠れる場所が多く魚たちにとって格好の住みかといえます。そのため、磯はさまざまな種類の魚が集まる絶好の釣りポイントです。
磯釣りのマナーとは?
磯釣りのマナーとは、自然と共存しながら安全に釣りを楽しむための基本的な心得です。
まず、磯場には立入禁止区域や漁業権が設定された場所があり、無断で入ると事故や法的トラブルにつながるおそれがあります。
看板や地元漁協の案内を確認し、立ち入りが許可された安全な場所を選びましょう。また、ゴミや釣り糸を残さないことも重要です。放置された仕掛けは、景観を損ねるだけでなく生き物に被害を与えます。
さらに、磯は足場が不安定で滑りやすいため、滑り止め付きのブーツやライフジャケットの着用を徹底しましょう。これらを守ることが、釣り人としてのマナーの基本です。
事前に必ず確認すべきルール
磯釣りは自然と密接に関わる釣りのため、事前の準備と情報収集が何より大切です。安全に楽しむためにも、出発前に天候や波の状況、立入禁止区域などをしっかり確認しましょう。
以下の基本ルールを参考に、磯釣りの前には必ず安全チェックを行うことを習慣にしてください。
立入禁止区域や遊漁規則を確認する
磯場の中には、立入禁止や漁業権が設定されている場所があります。看板の指示や地元漁協の情報を必ず確認しましょう。
無断で立ち入ると事故のリスクだけでなく、法的なトラブルにも発展します。
立入禁止区域と設定されている場所には絶対に入らず、安全な場所で釣りを行いましょう。立入禁止区域への進入は法令違反で検挙される場合があります。
引用元:海上保安庁|各釣り場での注意点
特に初めて訪れる地域では、事前に「○○県 遊漁規則」などで検索しておくと安心です。安全な釣り場を選ぶことが、マナーの第一歩といえます。
釣りをしたい磯場の漁業権について調べる際には、海上保安庁の海洋状況表示システム「海しる」がおすすめです。

「海しる」の使い方は、以下を参考にしてください。
「海しる」で漁業権の範囲を調べる方法
- 漁業権区画というページを選択すると、地図が表示されます
- 画面の左側にあるレイヤーにある「区画漁業権」「定着漁業権」「共同漁業権」の中から調べたいものを選ぶ
- 地図上に漁業権の範囲が枠(区画漁業権は青枠、定置漁業権は赤枠など)で表示されるので、調べたい範囲を確認する

天候・波の高さを事前に確認する
磯釣りでは「風」と「波」が最大の敵です。釣行前に気象庁や海上保安庁の波予報を確認し、少しでも高波や強風の予兆があれば中止しましょう。
風が強く波が高い日の釣りは危険です!
釣りに行く前に「気象・海象」を必ず確認しましょう。
引用元:海上保安庁
風が強いと波しぶきで足場が濡れて滑りやすくなり、体があおられてバランスを崩すこともあります。

マリーナスタッフである私の経験で言うと、風速が5m/sを超える日や、波の高さが1.5m以上ある日は非常に危険です。
波が高い日は突然の大波にさらわれるリスクが高まります。少しでも危険を感じる天候のときは、無理をせず釣行を中止する判断が大切です。
ほかの釣り人へのマナー

磯釣りでは、限られたスペースに多くの釣り人が集まるため、他の人との距離感や立ち回りに気を配ることが大切です。
釣り座の間隔を保つ、先に入っている人を優先する、仕掛けやキャストの方向に注意する。こうした基本的なマナーを守るだけで、トラブルを防ぎ、お互いが気持ちよく釣りを楽しめます。
ここでは、磯釣りで意識しておきたい他の釣り人への配慮のポイントを紹介します。
ほかの人の釣り座には近づきすぎない(目安5〜10m以上)
磯釣りではキャストや仕掛けの範囲が広いため、他人との距離を保つことが大切です。最低でも5〜10mは間隔を空けましょう。
距離が近いとほかの釣り人と糸が絡まるトラブルや、投げる際に竿や仕掛けの接触など思わぬ事故につながります。お互いが気持ちよく釣りを楽しめるように、譲り合いの気持ちを持つことが大切です。
先に入っている人を優先する
釣りには「先行者優先」という暗黙のルールがあります。これは、先にその場所に入った人が、そのエリアで釣りを楽しむ権利を持つという考え方です。
特に磯釣りは釣り座(※釣るための場所)が限られており、良いポイントほどスペースが狭いため、後から来た人が無断で隣に入ると仕掛けが絡んだり、トラブルに発展することがあります。
もし近くで釣りをしたい場合は、必ず一声「ここ使ってもいいですか?」と確認することが大切です。

その一言だけでお互いが気持ちよく釣りを楽しめますし、相手の状況によっては譲ってもらえることもあります。
また、釣り座を離れるときも、道具を広げたまま放置するのはマナー違反です。離れる場合は竿や荷物を片付けて、他の人が使えるようにしておくと親切です。磯釣りでは限られたスペースを共有する意識を持つことが、トラブル防止と良好な人間関係につながります。
仕掛け・キャスト方向を確認してから釣りをする
仕掛けを投げる前には、周囲の安全確認が欠かせません。特に磯場では人の出入りが多く、背後を通る人や隣の釣り人に糸がかかると、ケガやトラブルの原因になります。
振りかぶる前に一度後ろと左右を見て、人がいないか確認する習慣をつけましょう。
また、風のある日は仕掛けが流されやすく、意図しない方向に飛ぶことがあります。風向きに対して正面から投げず、少し角度を調整することで安全にキャスト(※竿を振って仕掛けを飛ばすこと)できます。
周囲の釣り人のラインと交差しないよう、投げる方向を相談したり、声をかけ合うこともマナーの一つです。小さな配慮が大きな事故を防ぐことにつながります。
知らない釣り人にも軽い挨拶をする
「おはようございます」「隣、使っていいですか?」といった一言があるだけで、釣り場の雰囲気は大きく変わります。軽い挨拶はトラブルを防ぐコミュニケーションツールです。無言で近づくよりも、ひと声かけることでお互いに安心して釣りを楽しむことができます。
さらに、挨拶を交わすことで信頼関係や助け合いのきっかけが生まれやすいです。

たとえば、トラブルが起きたときに助けてもらえたり、潮の流れや釣れるポイントなど釣りに関する情報交換ができることもあります。
磯釣りは限られたスペースを共有する釣りだからこそ、周囲との良好な関係づくりが大切。他の釣り人に軽くでいいので挨拶をして、安全で快適な釣行を心がけましょう。
自然環境を守るためのマナー

磯釣りは豊かな自然の中で楽しむ釣りだからこそ、環境への配慮が欠かせません。美しい磯場を次世代に残すためにも、釣り人一人ひとりが自然を守る意識を持つことが大切です。
ここでは、釣り場を汚さないための行動や生き物・周辺住民への配慮など、磯釣りをする上で守るべき環境保全のマナーを具体的に解説します。
岩場の貝や海藻は採らない
磯には貝やカニ、ヤドカリ、海藻など、無数の生き物が暮らしています。生き物は磯の生態系を支える大切な存在です。例えば、貝類や海藻は水質を浄化し、小魚の隠れ家にもなっています。

こうした生物をむやみに採取したり、岩をはがしたりすると、環境バランスが崩れ、魚の数が減る原因にもなります。
また、地元漁協が管理する磯では、採取行為が法律で禁止されていることも知っておかなければなりません。神奈川県の公式サイトでは、貝類や海藻類を採る行為について、以下のような記載があります。
共同漁業権が設定されている漁場内では、アワビ・サザエ等の貝類、ワカメ・コンブ等の海藻類、イセエビやタコ等共同漁業権の対象となっている水産動植物を組合員以外の者が採ると漁業権侵害となる恐れがありますので、そのような漁場では採らないようにしましょう。
引用元:神奈川県ホームページ|磯遊びのルールを守りましょう
生き物を持ち帰るのではなく、観察するだけにとどめることが釣り人のマナーです。「触らない」「壊さない」「持ち帰らない」を意識することで、自然と共に釣りを楽しむことができ、将来的にも釣り場を守ることにつながります。
声の大きさに注意して近隣住民への配慮を怠らない
早朝や夜の釣りでは、静かな環境の中で音が特に響きやすく、思った以上に遠くまで声や物音が届きます。
磯場の近くには住宅や民宿がある場合も多く、大声での会話やスピーカーでの音楽は、近隣住民への迷惑になることがあるので注意をしなければなりません。こうした騒音トラブルは、地元の人々との関係悪化や釣り場の立入制限につながることもあります。
また、静かに釣りをすることは、人だけでなく魚にとっても好条件です。魚は水中の振動や音に敏感で、大きな音を立てると警戒して逃げてしまうことがあります。

特に夜釣りの際は、ライトの扱いや足音も慎重に。
釣り人同士、必要最低限の声かけでコミュニケーションをとり、自然と共存する「静かな釣り時間」を大切にしましょう。
ゴミ・釣り糸はすべて持ち帰る
釣り糸やルアーを放置すると、鳥や魚が絡まって命を落とすケースがあります。特に磯場では、潮の流れで仕掛けが流され、遠くの海や岩場に引っかかることも少なくありません。
見た目以上に影響範囲が広く、釣り人自身が気づかぬうちに環境被害を起こしてしまうことがあります。
使い終わった仕掛けや糸は、必ず持ち帰ることが最低限のマナーです。

市販の「釣り糸回収ポーチ」や「仕掛け専用処理袋」を活用すれば、安全かつ簡単に回収できます。
また、他の人が残した糸やゴミを見つけた際にも、環境を守るために拾う意識を持つとより良いです。こうした小さな行動が、釣り人全体の印象を良くし、自分たちの釣り場を守ることにつながります。
磯釣りでの安全対策
磯釣りでは、自然の中で釣りを楽しむ反面、足場の悪さや波の強さなど多くの危険が潜んでいます。安全対策を怠ると、転倒や落水といった重大な事故につながることもあります。
ここでは、釣行前の準備・装備の選び方・緊急時の行動といった、磯釣りを安全に行うための基本的な対策をわかりやすく解説します。
ライフジャケットは必ず着用する(「桜マーク」を推奨)

磯釣りでは、足場の悪い岩場で滑って海に落ちる事故が毎年発生しています。特に波打ち際や濡れた岩の上は非常に滑りやすく、釣りの最中にバランスを崩して転落するケースも少なくありません。
ライフジャケットを着けているかどうかで、万一の事故時に生死を分けることもあります。
ライフジャケット着用時の生存率は約69.7%であるが、非着用時の生存率は約44.9%であり、ライフジャケットを着用した場合の生存率は非着用の場合と比べて約1.6倍高い。
引用元:海上保安庁『釣り中の事故発生状況について(PDF)』
こうした万が一の事態に備えて、ライフジャケットは命を守る最も重要な装備です。
購入の際は、国土交通省が安全基準を満たした製品に付与する「桜マーク」が付いたものを選びましょう。これは、一定の浮力と性能が保証された信頼の証です。
国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、 桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。
引用元:国土交通省|海事:ライフジャケットの着用義務拡大
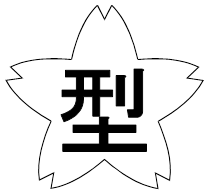
ベスト型タイプは動きやすく、収納ポケットも多いため、仕掛けや小物を入れておくのにも便利です。

たとえ海が穏やかな日でも「今日は大丈夫」と油断せず、釣りをする際は必ず着用する習慣をつけることが大切です。
安全対策の基本として、常に身につけておきましょう。
単独釣行は避けて家族や友人に行き先を伝える
磯釣りは自然の中で行うため、万が一トラブルが発生した際に、「助けを呼べない」という状況が最も危険です。特に足場の悪い岩場や波の荒い場所では、滑って転倒したり、急な高波に足を取られる事故も起こりやすく、一人では対応できないことがあります。
そのため、初心者のうちは必ず経験者や仲間と一緒に釣行するのが基本です。同行者がいれば、危険を察知して避難を促したり、緊急時に救助を要請することができます。
また、出発前には家族や友人に「行き先」「釣りをする時間」「帰宅予定時刻」を伝えておきましょう。予定を共有しておけば、もし帰りが遅れた際に早期の連絡や捜索につながります。

さらに、スマートフォンの位置共有アプリ(例:LINEの現在地共有・Googleマップの共有機能など)を活用しておくと、万一のときも居場所を把握しやすく安心です。
釣りの技術よりもまず「安全に帰る」ことを最優先に考える意識が、磯釣りでは何より大切です。
危険を感じたら無理せず撤退する
波が高くなったり、足場が滑りやすくなったりと、少しでも危険を感じたら、迷わず釣りを中止してその場を離れましょう。磯は潮の満ち引きや風向きで一瞬にして状況が変わるため、「もう少し大丈夫だろう」という油断が重大な事故につながります。
特に岩場では、わずかな濡れた苔や海藻で足を滑らせることも多く、転倒や落水の危険性は常に隣り合わせです。
「あと1匹だけ」「もう少し粘れば釣れるかも」という欲を抑えることが、安全な釣り人の条件です。
撤退は負けではなく、次の釣行へつなぐための最善の判断です。

経験豊富な釣り人ほど、危険を感じたときにすぐ判断し、早めに撤収しています。
自然相手の釣りでは、「無理をしない」「撤退を恐れない」という意識こそが、命を守るためには最も重要です。
マナーを守って磯釣りを安全に楽しもう
磯釣りは、波の音や潮風を間近に感じながら自然と一体になれる魅力的な釣りです。魚との駆け引きや釣れた瞬間の達成感は、他の釣りでは味わえない格別のものがあります。
しかしその一方で、磯は常に危険と隣り合わせの場所でもあります。天候の急変・高波・滑りやすい足場・他の釣り人との接触など、思わぬトラブルが起こる可能性があります。こうしたリスクを回避するためにも、マナーやルールを守ることは「誰のためでもなく、自分自身の命を守る行動」です。
立入禁止区域には絶対に入らず、装備は安全第一で選び、他の釣り人との距離を保つこと。そして、ゴミを持ち帰る・生き物を乱獲しないなど、自然への思いやりを忘れない姿勢が大切です。
磯釣りのマナーをしっかり身につけることで、釣果だけでなく、心から「また来たい」と思える豊かな体験になります。自然と共に釣りを楽しむ意識を持ち、安全で美しい磯釣りライフを楽しみましょう。




コメント