この記事では、渓流釣りのマナーやルールを紹介します。
渓流釣りについて「遊漁券や禁漁期間などのルールがわからない」「マナー違反でトラブルにならないか不安」と思っている人も多いのではないでしょうか。
そこで、地域ごとのルールの確認方法や現場で守るべきマナー、写真撮影や安全装備までをわかりやすく解説します。
さらに、釣行計画の立て方も紹介するので、この記事をチェックし、初心者の方も安心して渓流釣りを楽しんでください。

この記事を書いた人
F!ND編集部_コウイカ
現役マリーナスタッフであり、10年以上のマリーナ勤務歴がある。自身も釣りやが好きで、最近はジギングやエギングにハマっている。
渓流釣りを始める前に知っておくべき基本ルール

渓流釣りには地域ごとの管理規則があり、遊漁券や禁漁期間など必ず守るべき決まりがあります。
ここでは、渓流釣りでの基本ルールを紹介するので、渓流釣りをこれから始めようと思っている人はしっかりと確認しておきましょう。
「遊漁券」を購入する
多くの渓流は漁協が管理しており、釣りをするには遊漁券の購入が義務付けられています。無券で釣りをすると法律違反となり、罰金を科される場合もあるので注意が必要です。
福岡県庁の公式サイトを見てみると、遊魚券について下記の記載がありました。
遊漁券を購入せずに遊漁を行った場合、漁業権侵害に問われる場合があります。漁業権侵害をした者は、漁業法により100万円以下の罰金に処せられます。
引用元:福岡県庁ホームページ|内水面の遊漁のルール
遊漁券は地元の釣具店やコンビニ、渓流を管理している各漁協の公式サイトなどで購入できます。釣行当日の購入も可能ですが、事前にオンラインで買っておけばスムーズです。

日券・年券などいくつか種類があるので、釣りをする頻度に合わせて適切な遊魚券を選びましょう。
禁漁期間を把握しておく
渓流では魚の繁殖を守るため、地域ごとに禁漁期間が設定されています。多くの河川では秋から翌春までが禁漁期となり、その間の釣りは禁止です。
たとえば、渡良瀬漁業協同組合の公式サイトでは、渓流解禁日について下記の記載がありました。
渓流釣り〈全河川〉 3月2日(日)日の出から9月19日(金)日没まで
引用元:渡良瀬漁業協同組合|河川・魚種・釣り場案内
このように地域によって渓流解禁日が決められており、禁漁期間中の釣行は罰則の対象となります。
渓流釣りの前に、漁協や県の「漁業調整規則」を公式サイトなどで確認しましょう。
河川によっては釣法や対象魚種ごとに細かい規定がある場合もあります。釣りをする河川のルールを確認することも忘れないようにしましょう。
漁協・県公式サイトでルールを確認しておく
遊漁券や禁漁期以外にも、釣り方・持ち帰り可能な魚のサイズ・使用できる餌やルアーなど、細かいルールが定められています。
公式サイトには最新情報や地図が掲載されており、確認しておくことで現場でのトラブル防止に役立つでしょう。
- 禁止漁法の例
アユのえさ釣り、オランダばり、土管釣り類(まき餌、練り餌の使用を含む)、リール使用の鮎釣り(掛け釣りを除く)漁法は禁止です
サクラマス、ヤマメ、イワナは竿釣り以外できません
引用元:渡良瀬漁業協同組合|入漁のルールとマナー
釣行予定の河川が複数にまたがる場合は、隣接する漁協の規則も併せて確認しておくと安心して釣りを楽しめます。
現場で守るべきマナー

渓流釣りは自然と共存するレジャーであり、他の釣り人や地域住民への配慮が欠かせません。以下のポイントを守ることで、トラブルを避けつつ快適に釣りを楽しめます。
先行者への配慮と釣り上がりの作法を理解しておく
渓流釣りでは、川の下流から上流へ向かって歩きながらポイントを探る「釣り上がり」が基本スタイルです。
渓流魚は虫や餌を効率よく捕食するために、流れに対して上流を向いて泳いでいます。
そのため、魚の正面にあたる上流側から近づくと人影や動きが目に入りやすく、強い警戒を与えてしまい、結果として魚が散り釣果に悪影響を及ぼします。
先行者がすでに釣り上がっている場合は、無断で追い越したり、至近距離に割り込むことは厳禁です。

たとえ相手が休憩していても、近くで竿を出すのはマナー違反とされます。
どうしても同じ区間を釣りたい場合は「この上流を入らせてもらってもよろしいですか」と声をかけ、相手が了承した場合のみ距離を十分に保って入渓しましょう。
自然環境を守る行動を心がける
ゴミや糸くずは必ず持ち帰り、外来魚や余った餌を川に放流しないことが重要です。環境省も「自然公園でのルール・マナー」としてゴミの持ち帰りや外来種対策を呼びかけています。
自分を含めて渓流釣りをするすべての人が気持ちよく釣りができるように、河川沿いの植物を踏み荒らさない、焚き火をしないなど、自然環境を守る意識を常に持ちましょう。
写真撮影時の注意点
釣果をSNSでシェアする際は、魚や自然への影響に十分配慮する必要があります。渓流釣りをする人や地域に迷惑がかからないように、以下のことに気をつけましょう。
魚が弱らないように気をつける
撮影はできるだけ短時間で行い、魚体は水に浸けたままが理想です。素手で長時間持つと体表の粘膜が傷つき、感染症や死亡のリスクが高まります。
魚を持つ際は濡れた手袋やウェットタオルを使用して、魚が弱らないような対策をしましょう。
キャッチ&リリース時の手順を覚える
リリースする場合は、バーブレスフック(返しのない針)を使用し、魚が自力で泳ぎ出すまでサポートします。無理に針を外そうとせず、プライヤーなど専用器具を使って素早く処理することで魚へのダメージを最小限に抑えられます。
▼バーブレスフックのイメージ


はじめは針を外す作業はむずかしいかもしれませんが、少しでも魚にダメージを与えないように、丁寧に扱うことを心がけておきましょう。
SNSに投稿する場合は、場所を特定されないようにする
人気スポットが過剰利用されると環境悪化につながります。写真に背景を入れる場合は位置情報をオフにし、川の特徴がわかる地形を避けるなど、投稿時の配慮が必要です。
釣果をSNSに投稿したい場合は、魚や人物をできるだけアップにするなど、ちょっとした工夫で、場所を特定されることを回避できます。
安全対策と装備の基本
渓流には、急な増水や滑落などのリスクがあります。
大切な命を守るためには安全対策を徹底することが重要です。初心者でも安心して渓流釣りを楽しめるように、以下の内容をチェックしてみましょう。
安全装備を準備する
滑り止め付きウェーダー(防水性のズボンとブーツが一体になったもの)、ライフジャケット、防水ケースに入れたスマートフォンは準備しておきたい安全装備です。
熊が出やすい地域で渓流釣りを行う場合は、熊対策の鈴も用意しておくと良いでしょう。
もしもの場合に備えて単独釣行は避け、仲間と一緒に行動することも渓流釣りをするときには大切です。
事前に天候・水位チェックしておく
前日の雨や上流のダム放流で急に水位が上がることがあります。水位が上がり始めたらすぐに釣りを中止することが重要です。これくらいは大丈夫だろうという軽い気持ちが大事故につながってしまいます。
渓流釣りをする際には、事前に国土交通省の水位情報や気象庁の天気予報を必ず確認し、少しでも危険を感じたらすぐに釣りを中止することを心がけましょう。
国土交通省「川の防災情報」サイトでは、釣行予定地周辺の水位情報・降雨データ・河川カメラ映像をリアルタイムで確認が可能です。地図上で観測所やライブカメラを選べば、実際の川の様子や濁り具合が把握できます。

さらに、地域ごとの河川事務所やダム管理者サイトでは放流通知や放流予定情報も公開されているため、国土交通省のサイトと併用することで危険を事前に察知可能です。

安全第一を心がけ、少しでも異変を感じたらすぐに撤収する勇気を持ちましょう。
初心者は釣行計画を立てよう!
初めての渓流釣りは、計画を立てることで安全性と釣果が大きく向上します。
- 行きたい河川の漁協情報を公式サイト等で調べる
- 遊漁券の購入方法を確認
- 禁漁期間や釣法ルールを把握
- 装備チェックと天候確認
前日までに釣行計画をしっかり立てて準備を済ませておくと、当日は釣りに集中でき余計なトラブルを防げます。
渓流釣りのマナーを守って楽しく釣りをしよう
渓流釣りは美しい自然と魚との駆け引きを楽しめる魅力的なレジャーですが、遊漁券や禁漁期間などの公式ルール、他の釣り人への配慮、環境保護、安全装備など守るべきポイントが多くあります。
事故やトラブルに合わないためにも、事前に自治体や漁業組合の公式サイト等で情報を確認することが大切です。マナーやルールをしっかり守って渓流釣りをして、自分自身の安全と豊かな渓流環境を未来へ残していきましょう。
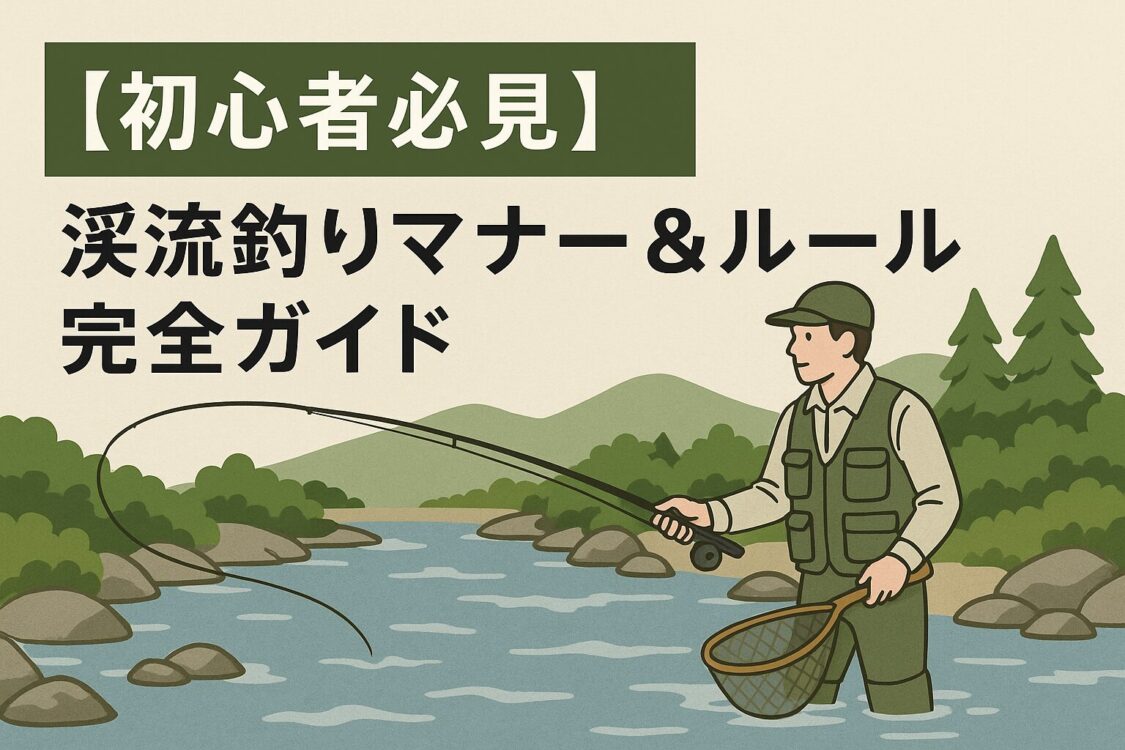
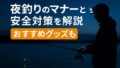

コメント